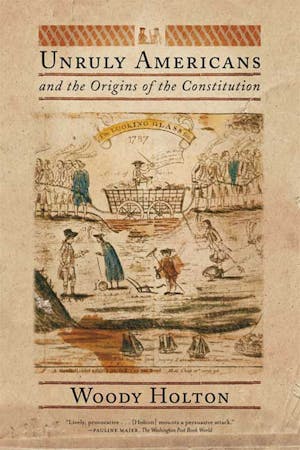森先生から招待いただきました、九大修士2年の高橋と申します。帝国史の観点から海軍強制徴募と初期アメリカの船乗り研究をやっています。どうぞよろしくお願いします。
先生方、数々の貴重な史料・文献・学会などの情報を紹介下さり、感謝申し上げます。まだまだ勉強不足で、情報集めに四苦八苦しているので大変助かります😂
さて、私のほうからは史料読解の成果を挙げていければと考えております。現在、修論に向けて船乗りの日記を読んでいるところです。Massachusetts Historical Societyのオンラインカタログから、森先生にご協力いただいてみれるようになった史料です。
Pre-Revolutionary Diaries at the Massachusetts Historical Society, 1635-1790 (masshist.org)
↑この日記集に所収されているベンジャミン・バングス(Benjamin Bangs)という船乗りの日記です。
バングスはマサチューセッツ植民地バーンズダブル郡ハーウィッチに住んでいた白人ピューリタンで、捕鯨や漁業に携わる船のオーナー(祖父や曾祖父も船のキャプテンだった模様)でした。初期ピューリタン(おそらくイングランドからプリマスに移住)の子孫で、墓石(下画像)も残されております。白人の多いマサチューセッツの典型的な多数派だったといえると思います。
(出典 Benjamin Bangs (1721-1769) - Find a Grave Memorial 最終閲覧2022/07/24)
彼は22歳のときから日記を書き貯め、①1742-49、②1759-61、③1761-63、④1763-65の計4冊が残っています(残念ながら1750-58の期間のものは消息不明)。
私はいわゆる「第一次帝国」期に関心があるので、①を読み進めているところですが、海軍強制徴募(naval impressment, 史料だとpressやprest, impressedなどの単語で登場する)に関する話が散見されます。
バングスの史料自体のうち①は船乗りの日常史(Magra 2009)などで引用されてきました。
最近では、アメリカ独立革命史を帝国史や大西洋史の成果も踏まえて強制徴募と民衆暴力の観点から描き切ったクリストファー・マグラの著作(Magra 2016)で、1747年のボストン反強制徴募暴動やそれ以前の強制徴募の目撃証言の記述が引用されています。
↓日記の形式はこんな感じです。
左縦一列に日付が書かれていて、大体1日1~3行ずつのその日の内容が書かれています。日々の風向きや天気、漁業や取引の成果などが多く書かれているので、日記というより航海日誌の側面も強いのですが、本人が冒頭で
「ベンジャミン・バングスの人生に関するメモと端的な記録。自己満足のためにいくつかの報告書と注目すべき出来事も含む。a memorandum or short acc[oun]t of my Life of Benj[ami]n Bangs containing some Transactions and most Remarkables for my own satisfaction」(冒頭2ページ)
と書いているように、フランスの私掠船や強制徴募との遭遇についてや、本国のニュースもときどき書かれています。
例えば以下の一節。
「私たちはボストンに到着し、激しいホットプレス(緊急強制徴募)を恐れて麦の中に隠れた。We came out and got to Boston & hid in the oats for fear of the press which is very hot.」(1743/10/19, 20)
ボストンで強制徴募に遭遇しかけたバングスは、船に積んでいたであろう麦の中に隠れています(この前の日に、粉屋と一緒にボストンに向かう予定だと書かれていました)。バングスは1740年代の間に何度もこの強制徴募に関する記述をしておりますが、当時ブリテン帝国を支えた王立海軍のリクルート手段である強制徴募との遭遇が決してまれではなかったことが垣間見えます。
他にも、船の乗組員として先住民を抱えていたり、1760年代には奴隷貿易に携わっていたりと、マサチューセッツの白人ピューリタンながらも最近のアメリカ史研究でホットな観点から色々分析できそうな面白い史料だと思っています。さらには、宗教史(ニューライトやホィットフィールドに関する記述あり、Winiarski 2017)の文脈でもこの史料の研究が進みつつあるようです。
マサチューセッツという、古来は「普遍」的なモデルだとされ、グリーンらによってヴァジニアなどとの比較からかえって「特殊」だとされた植民地の中にも、船乗りというミクロレベルの視点を主軸にしつつ、大西洋史や帝国史の観点、さらには人種などの観点から切り込める余地があるのでは…と思って読解を進めております。手稿史料なので文字起こしから始まり大変ですが、今から200年近くも前のひとびとの書いたものを掘り起こしていると思うと感慨深いものがあります。
未熟な若輩者ですが、ためしに投稿してみました。先行研究の理解や史料分析に関して、浅いところも多いかと思います。なにかお気づきの点がありましたらコメントでご助言等いただけると大変有難いです。
今後も史料読解の成果の一部を少しずつ投稿してみようかと存じております。
どうぞよろしくお願いします。
<参考文献>
Magra, C. P. 2009: The Fisherman's Cause: Atlantic Commerce and Maritime Dimensions of the American Revolution. Cambridge.
Magra, C. P. 2016: Poseidon's Curse:
British Naval Impressment and the Atlantic Origins of the American Revolution,
Cambridge.
Winiarski, D. 2017: Darkness Falls on the Land of Light: Experiencing Religious Awakenings in Eighteenth-Century New England, North Carolina.
(高橋)